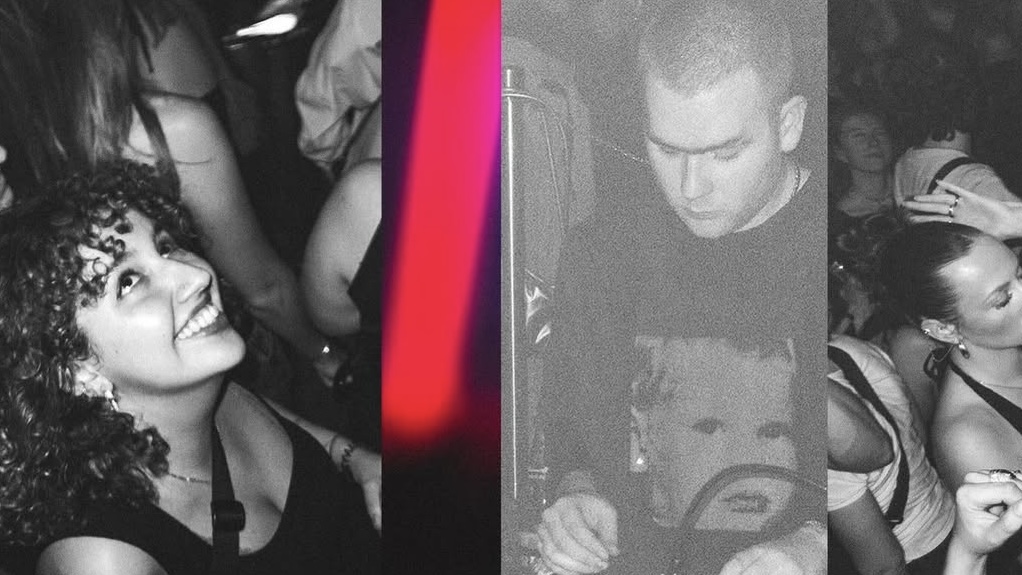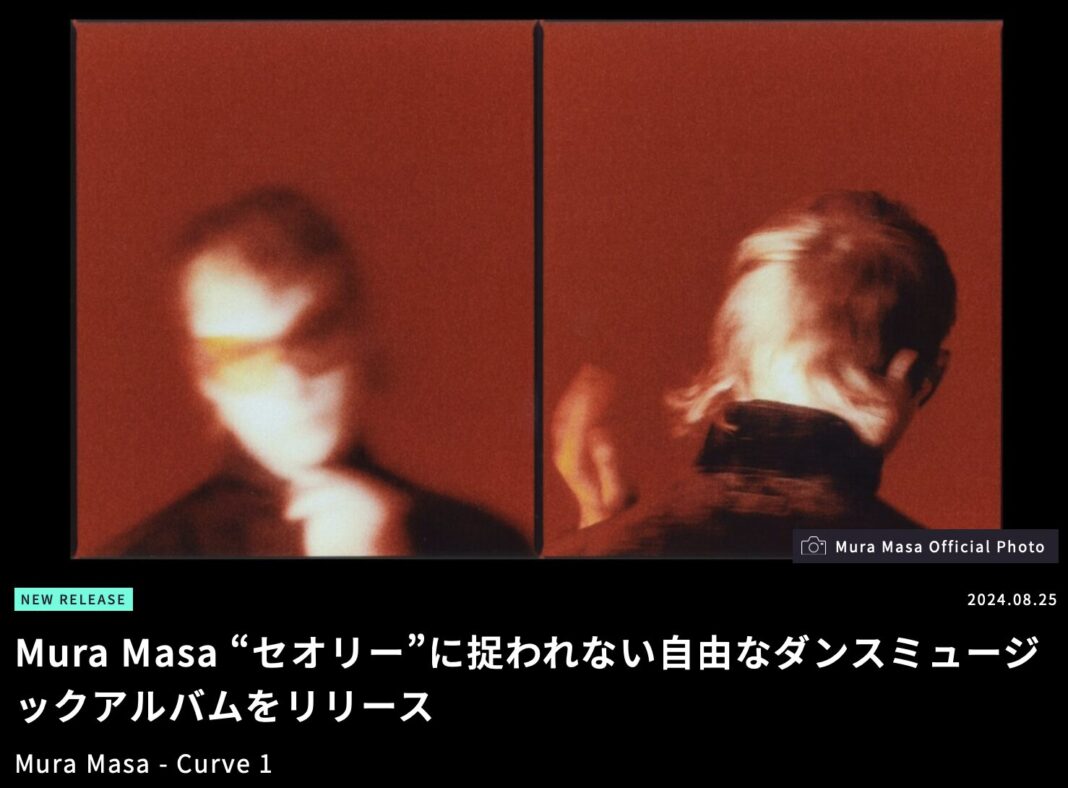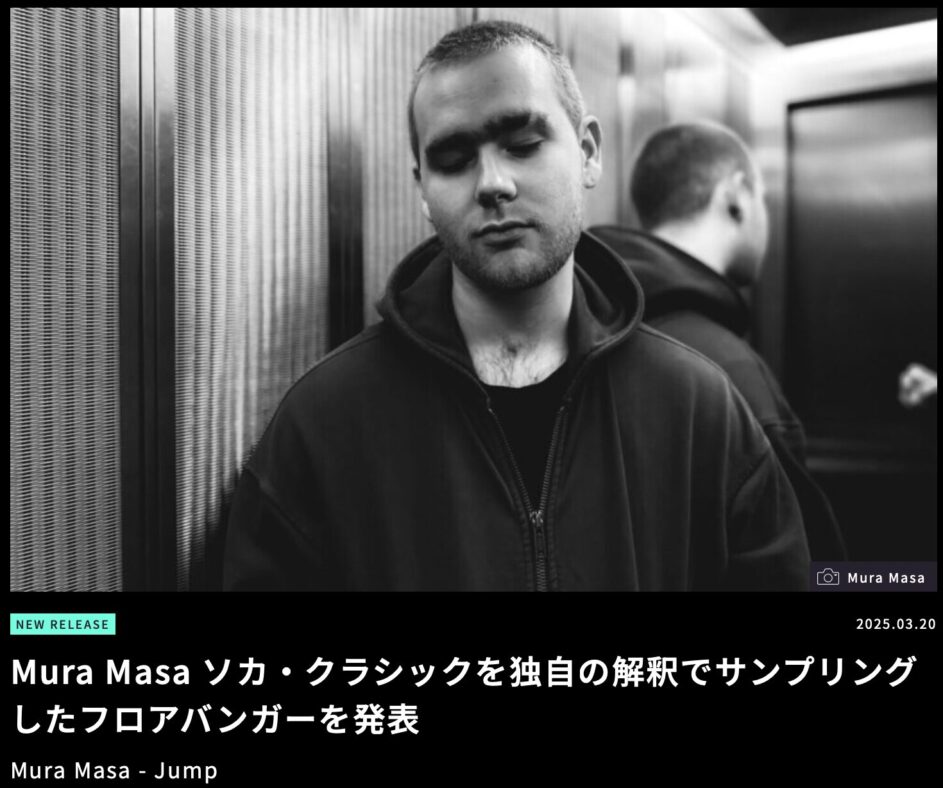UK出身のプロデューサー、Mura Masa(ムラ・マサ)が最新EP『Curve +1』をリリースした。
グラミー受賞経験を持つ彼にとって、本作は前作アルバム『Curve 1』の延長線上にありながら、わずか4曲というミニマルな構成で「量より質」というメッセージを明確に打ち出した作品である。短い収録時間ながらも、彼なりのダンスミュージックの「今」を鮮やかに描き出す濃密な内容に仕上がっている。
Mura Masa “セオリー”に捉われない自由なダンスミュージックアルバムをリリース
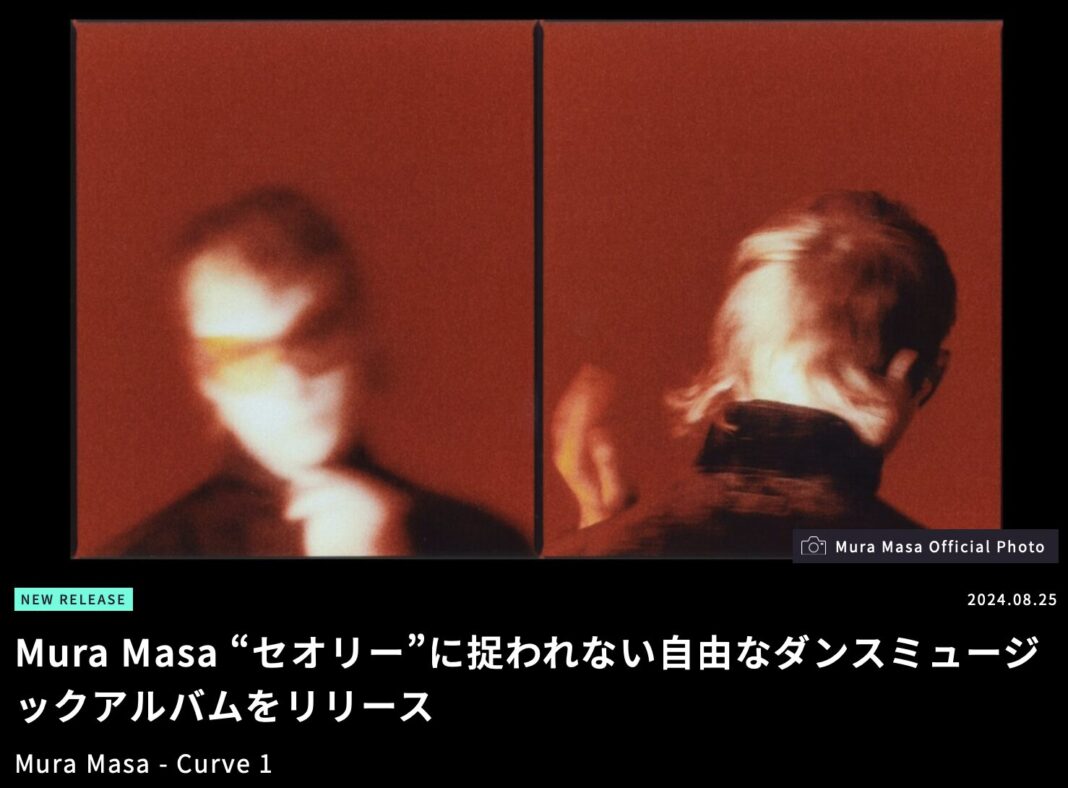
EPを牽引するのは、先行公開された「JUMP」と「I’m Really Hot (For Myself)」だ。「JUMP」は1995年、Zulu Lightningによるソカ・クラシック「Hold Up Yuh Foot & Jump」をサンプリングし、現代的にアップデート。ニューヨークのダブルダッチチーム *Showdem Movement* を起用したMVでも話題を集め、ストリートカルチャーの熱気を現代のクラブ仕様に落とし込み、映像と音の両面で躍動感を体現している。
Mura Masa ソカ・クラシックを独自の解釈でサンプリングしたフロアバンガーを発表
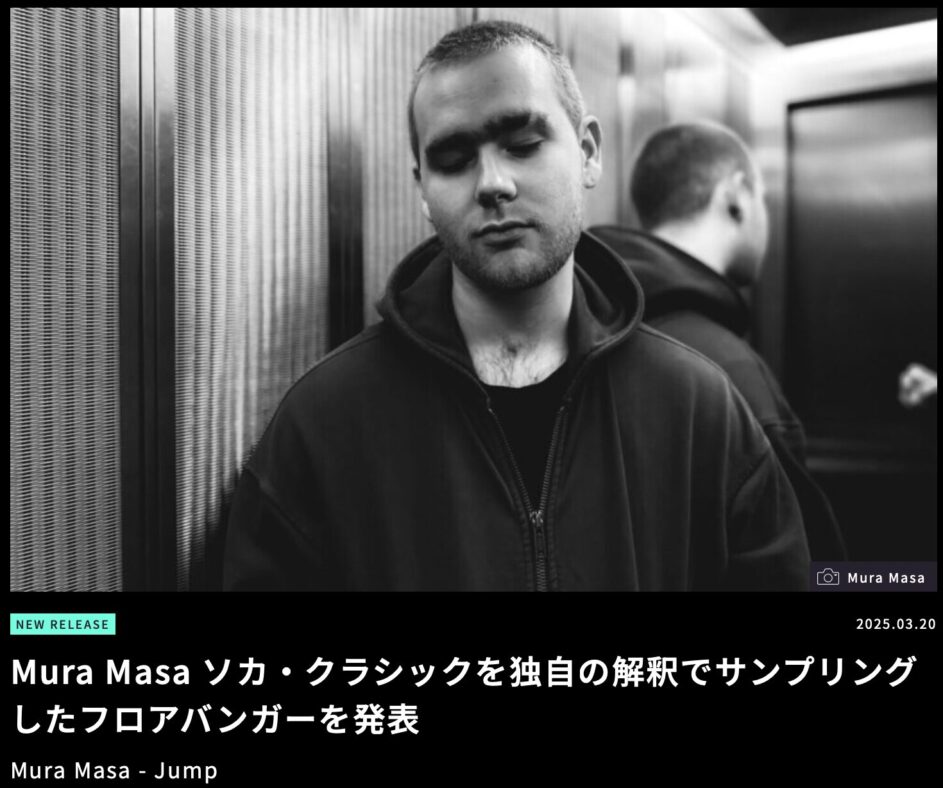
一方の「I’m Really Hot (For Myself)」は、Missy Elliottの2003年同名作を想起させる四つ打ちのダンス・ジャム。インパクトあるギターリフにインダストリアルな質感を帯びたざらついたビートが加わり、ジャンルを越えてフロアで機能する強度を持つ。The Reidsが監督を務めたMVでは、双子ダンサー Jay & Georgia Lance が登場し、自己愛をテーマにした振付を披露。Mura Masaは「誰かのためにホットになるのではなく、自分のためにホットである」というアイデアを込めたと語っており、クラブ・トラックでありながらメッセージ性も帯びた作品となっている。
新曲「Losing」はソウルフルなコード感とヴォーカルサンプルを軸にしたハウス・チューン。トライバルで温かみのある前半から、後半にはブレイクビーツとアシッド・ベースが入り混じり、静けさの中にカオスを孕んだ感情的な展開を見せる、彼らしいユニークな1曲だ。
「Handsup」はオールドスクールなヒップホップの質感を持つイントロから、西海岸のGファンク的なシンセリードが絡む軽快なマイアミベース〜2Step的なビートへと展開。ピッチを上げたヴォイスサンプルがレトロなバイブスを漂わせながらも、曲は次第に加速し、狂気じみたジャングル・ビートへとなだれ込む。UKガラージ/エレクトロファンクからドラムンベースへと縦断する構成は、英国クラブカルチャーの歴史を凝縮したようであり、現場での爆発的な反応が目に浮かぶ。序盤で聴き手を心地よく誘い込み、終盤でカオティックな熱狂へ導く展開は、まさにレイヴの初期衝動を凝縮したものだ。
1996年生まれのMura Masa(本名 Alex Crossan)の名前は、日本の刀鍛冶「村正」に由来する。10代でSoundCloudに投稿した楽曲が注目を集め、2017年のデビュー・アルバム『Mura Masa』で一躍ブレイク。同作にはCharli XCXやA$AP Rocky、Damon Albarnなどが参加し、2018年のグラミー賞「最優秀ダンス/エレクトロニック・アルバム」「最優秀録音パッケージ」にノミネートされた。2019年にはHAIM「Walking Away (Mura Masa Remix)」でグラミー賞「最優秀リミックス・レコーディング賞」を受賞。
ダンス、ポップ、オルタナ、ヒップホップをまたぐ幅広い層から支持を集めている。近年はPinkPantheress「Boy’s a Liar」諸作をはじめ、Ariana Grande、Shygirl、BTS、LE SSERAFIMなど多彩な作品を手掛け、ポップの感性とクラブ機能性を兼ね備えたプロデューサーとして注目を浴びている。また、自身のレーベル兼クリエイティブ・コミュニティ〈The Pond〉を設立し、クラブ志向を鮮明に打ち出しつつ、新進アーティスト支援やコラボレーションの拠点としても活動を展開している。
『Curve +1』はわずか4曲にして、Mura Masaの現在を濃縮した作品だ。また今回のリリースは、進行中のヨーロッパ巡回ツアー「Curve」ともリンクしており、バルセロナ、ベルリン、アントワープ、アムステルダムを経て、11月24日にはロンドン・ラウンドハウスでフィナーレを迎える。新曲が各地でどのようにセットに組み込まれ、観客と交錯するのか。その現場感を含めて「+1」の存在感はさらに高まっていくだろう。